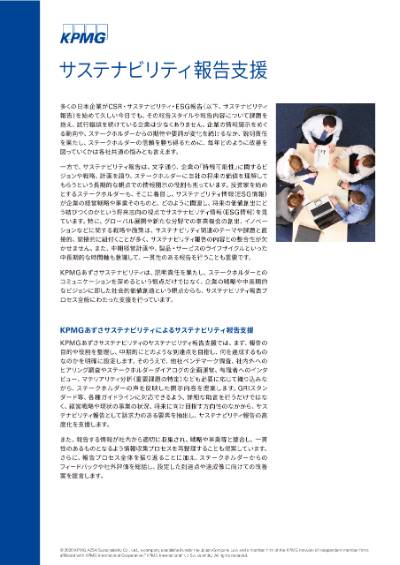サステナビリティ報告支援
開示すべき重要な側面の特定へのアドバイス、ESG指標の評価に関連する情報開示のアドバイス等、サステナビリティ報告の高度化を支援します。
開示すべき重要な側面の特定へのアドバイス、ESG指標の評価に関連する情報開示のアドバイス等、サステナビリティ報告の高度化を支援します。
多くの日本企業が CSR・サステナビリティ・ ESG報告(以下、サステナビリティ報告)を始めて久しい今日でも、その報告スタイルや報告内容について課題を抱え、試行錯誤を続けている企業は少なくありません。企業の情報開示をめぐる動向や、ステークホルダーからの期待や要請が変化を続けるなか、説明責任を果たし、ステークホルダーの信頼を勝ち得るために、毎年どのように改善を図っていくかは各社共通の悩みとも言えます。
一方で、サステナビリティ報告は、文字通り、企業の「持続可能性」に関するビジョンや戦略、計画を語り、ステークホルダーに自社の将来の価値を理解してもらうという長期的な観点での情報開示の役割も担っています。投資家を始めとするステークホルダーも、そこに着目し、サステナビリティ情報( ESG情報)が企業の経営戦略や事業そのものと、どのように関連し、将来の価値創出にどう結びつくのかという将来志向の視点でサステナビリティ情報( ESG情報)を見ています。特に、グローバル展開や新たな分野での事業機会の創出、イノベーションなどに関する戦略や施策は、サステナビリティ関連のテーマや課題と直接的、間接的に紐付くことが多く、サステナビリティ報告の内容との整合性が欠かせません。また、中期経営計画や、製品・サービスのライフサイクルといった中長期的な時間軸も意識して、一貫性のある報告を行うことも重要です。
KPMGあずさサステナビリティは、説明責任を果たし、ステークホルダーとのコミュニケーションを深めるという観点だけではなく、企業の戦略や中長期的なビジョンに即した社会的価値創造という観点からも、サステナビリティ報告プロセス全般にわたった支援を行っています。
KPMGあずさサステナビリティによるサステナビリティ報告支援
KPMGあずさサステナビリティのサステナビリティ報告支援では、まず、報告の目的や役割を整理し、中期的にどのような到達点を目指し、何を達成するものなのかを明確に設定します。そのうえで、他社ベンチマーク調査、社内外へのヒアリング調査やステークホルダーダイアログの企画運営、有識者へのインタビュー、マテリアリティ分析(重要課題の特定)なども必要に応じて織り込みながら、ステークホルダーの声を反映した開示内容を提案します。 GRIスタンダード等、各種ガイドラインに対応できるよう、詳細な助言を行うだけではなく、経営戦略や現状の事業の状況、将来に向け目指す方向性のなかから、サステナビリティ報告として訴求力のある要素を抽出し、サステナビリティ報告の高度化を支援します。
また、報告する情報が社内から適切に収集され、戦略や事業等と整合し、一貫性のあるものとなるよう情報収集プロセスを再整理することも提案しています。さらに、報告プロセス全体を振り返ることに加え、ステークホルダーからのフィードバックや社外評価を総括し、設定した到達点や達成像に向けての改善案を提言します。
サステナビリティ報告支援のステップ(例)と支援内容
サステナビリティ報告の中期的な開示方針と計画の立案
- 現状の情報開示の分析
- 情報開示の動向に関する調査
- サステナビリティ報告の目指す姿の設計
- 目指す姿の達成に向けた中期的な開示方針および計画の立案に対する支援
報告要素と報告プロセスの整理
- ベンチマーキング
- アンケート調査/ステークホルダーダイアログに対する支援
- マテリアリティ分析
- 報告要素の決定に対する支援
- 報告要素の情報収集プロセスの簡易調査・再整理
- 情報収集プロセスの改善に対する支援
サステナビリティ報告の実施
- 開示方針に沿った基本構成の決定への支援
- 報告内容の決定への支援
- 報告媒体(CSR報告書、サステナビリティ報告書等)の作成支援
次年度以降に向けた改善
- 次年度以降に向けた改善事項の洗い出し課題の決定を支援
- 改善事項への提案
新しい企業報告の枠組みへの対応
「GRIスタンダード」の改訂、「統合報告」のあり方についての議論の進展、CDPやTCFD(気候変動関連財務情報開示タスクフォース)提言に代表される気候関連財務情報の開示への期待など、サステナビリティ報告には新たな段階が訪れているといえます。こうした新しい企業報告の枠組みに対応するだけでなく、環境・社会・ガバナンス(ESG)の要素を考慮した投資行動を行う投資家が増えていることを捉え、そのような投資家をより意識した情報開示に舵を切る必要があります。
KPMGあずさサステナビリティは、日本におけるGRIデータパートナーとして、事実上のサステナビリティ報告の国際基準であるGRIスタンダードについて深い知見を有しているだけでなく、投資家の情報ニーズに関しても、さまざまなチャネルを通じてその動向を把握しています。
KPMGあずさサステナビリティは、こうした知見と豊富な報告支援実績に基づき、サステナビリティ報告で開示すべき重要な側面(Material Aspects)の特定へのアドバイス、あるいは、DJSIやFTSE4Goodなど代表的なESGインデックスにおける評価の裏付けとなる情報開示のアドバイスも含め、サステナビリティ報告の高度化を支援します。