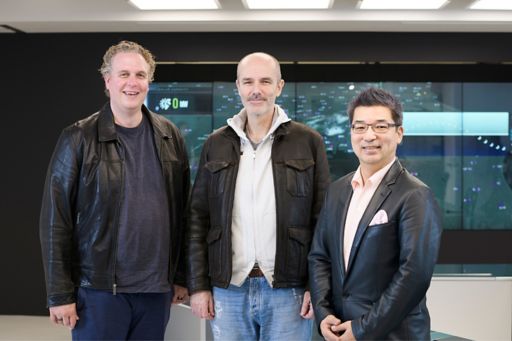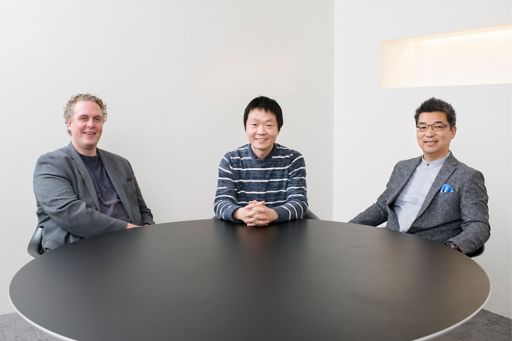ここ数年、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」というワードは使い古され陳腐化したと感じていた方も多くいたのではないでしょうか? しかし、昨年来のコロナ禍に直面することでDXがにわかに注目を集め、政府のテレワーク推進などがトリガーとなって企業におけるDXは大きく進展しました。
では、ポストコロナ以降の社会では、企業にとってDXは何を意味し、企業活動をどのように変えていくことになるのでしょうか? KPMG Ignition Tokyo(KIT)の茶谷公之とティム・デンリ、そして、KPMGコンサルティングの執行役員パートナーである佐渡誠が現状を整理しながら “妄想・空想”を巡らせてみました。
なぜDXを推進するのか? なぜイノベーションを起こさなければならないのか?
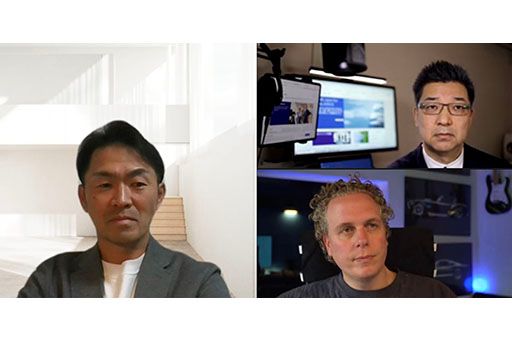
( KPMG コンサルティング株式会社 執行役員 パートナー 佐渡 誠(左)、株式会社KPMG Ignition Tokyo 代表取締役兼CEO、KPMGジャパンCDO茶谷公之(右上)、同取締役 パートナー ティム・デンリ(右下))※記事中の所属・役職などは、記事公開当時のものです。
茶谷: まずKPMGコンサルティングの中でDXをどのように捉えているのか、聞かせてください。
佐渡: KPMGコンサルティング内でもDXは議論が深まっているテーマです。順を追って説明すると、最初に「DX」の言葉が扱われ始めたのが1つ前の3ヵ年計画の時でした。今振り返ると、この時はまだ言葉が先行している状態だったように感じます。例えば、オペレーションやコーポレート部門、カスタマープロセスのデジタライゼーションに重きを置くというイメージで、具体的ではありましたが断面的になりがちでした。
しかし、徐々に「DXとはそういうものではない」と気付き、ようやく私たちの中で「DXとは?」の基軸ができてきました。
今では「企業そのもののビジネスモデルや収益の上げ方、オペレーションモデル全体を変える、過去の延長線上にはないデジタルインパクトを捉えなくてはいけない」といったDXの考え方に変わり、それに応じてどういった価値創造や人材の構成にしていくか、などを考え始めるようになっています。今まさに検討している新しい中期経営計画はそうした考えを踏まえたものです。
茶谷: なるほど。私たちKITでは「DXはCX(コーポレート・トランスフォーメーション)である」と打ち出してきました。これは、アナログをデジタルに置き換えるのではなく、会社全体のあり方や立ち位置など“デジタルではない部分”も含めて変化・進化する取り組みを意味しています。KPMGコンサルティングの皆さんと考え方が共鳴していてとても嬉しいです。
デンリ: 佐渡さんとは4年前からDXについて一緒に向き合ってきました。これは、組織体として実施しなければDXのインパクトが出せない、という思いがあったからです。
ところで、DXに絡んで、「破壊的なイノベーションを生むには(企業からその担い手を)独立させなければいけない」というのが少し前には主流の考え方になっていましたね。しかし、私は最近、「これは当たらない」と思い始めています。当時より変化のスピードが速い今日、独立させるというプロセスを踏んでいるほどの時間的余裕はないと感じるからです。
佐渡: そうですね。むしろ「なぜDXをしなければならないのか? なぜイノベーションを起こさなければならないのか?」と考えるスタンスが大切で、そのためには何らかの仮説を持たなければならないと考えます。
この半世紀にわたって“当たり前”と考えられてきたビジネスモデルの前提そのものが初めて変化する機会を迎えたと言えるでしょう。従来のコンサルティングは、切り口やモデルは変わってもビジネスの根幹自体は変わらない、という前提で行なわれていましたが、これからはビジネスモデルそのものを変えなくてはいけない、ビジネスモデルが変わることを前提に置きながらコンサルティングサービスを行わなければならなくなっています。
このことを経営者も私たちコンサルタントも理解した上で向き合わなくてはならないのです。「なぜDX、イノベーションを起こさなければならないのか?」その問いの本質を徹底して理解しなければなりません。
「今までも様々なことが変わってきた」と思われる方もいらっしゃるとは思いますが、それでも業界ルールやビジネスモデルの根幹は揺るがず、スケールや生産性を磨いてきたのがこの半世紀だったと私は見ています。しかし、現代を代表する企業であるGAFAに見られるように、ビジネスモデル自体や企業組織全体のオペレーティングモデルを抜本的に作り替えなければ立ち向かえない時代になっています。それが「Why DX?」の本質だと思います。
不確実な時代に強さを発揮する3つの機能
茶谷: ビジネスやオペレーティングモデルの変化が起こっている、というのはまさしくその通りで、その変化への適応方法は教科書や先行事例に答えがあるわけではありません。この点自体がこれまでとの大きな違いですが、この局面でどのような人材や力が必要になると考えていらっしゃいますか?
佐渡: 今考えているのは3つの能力です。まず、業界の将来を見る力で、未来志向的な業界先見性が挙げられるでしょう。2つ目は、デジタル・イネーブラー(デジタルの力や技術に知見を持ち、社内外から柔軟に調達・編み合わせて提供できる能力)です。3つ目は、データをビジネスバリューに昇華させられる力です。デジタル変革においてサステナブルな価値を作り出すのはデータです。そのデータをどのように活かすべきか、を考え提言出来る力、というイメージです。
これら3つの能力をKPMGジャパンが実装し、強化していくことによって、この不確実な時代でも力強く進んでいき、DXに向き合うこれからの時代に価値を提供できると考えています。

デンリ: 今の話を聞いていて、米国のデータアナリティクスチームのことを思い出しました。
オバマ政権時代、ポール・ボルカーFRB議長(当時)が提唱した「ボルカー・ルール」という金融規制が誕生しました。これに対し、各金融機関は自社の商品や取引内容等の全てを把握し、どのような部分でボルカールールに抵触するか、短期間で明確にする必要に迫られたものです。
金融商品の数は多く、その内容を記した書類は膨大であるため、すべてを理解するのに4年はかかる、とまで言われていました。そこで、KPMGは、商品をすでに理解している人を集め、AI領域を理解している人材でチームを編成し、最終的には2週間で問題解決にこぎつけたと聞いています。
この例はまさに佐渡さんが挙げた3つの能力を活用した結果だと言えるでしょう。このように、通常4年、最低でも2〜3年かかるところを2週間程度で対応するような「ハイパー・アジリティ」が今日のビジネスでは求められているのだと思います。
佐渡: これまでのコンサルティングは他社事例や成功・先進事例で話を進めることができましたが、今は私たちも手探りで不確実な未来を予測して進んでいる状態です。私たちのスタンスも大きく変わっており、先ほど挙げた3つの能力に加えて、より一層、言語を超えたクライアントとの協力も必要だと感じています。
また、今後は自分たちもどのようなリスクテイクをしていくか考える必要が出てくると見ています。「お客様に寄り添います」という姿勢だけではなく、具体的にどんなリスクテイクをするか示していかなければ時代とは合わないと感じます。
企業の価値は「タレント・データ・テクノロジー」で測られる

茶谷: このところ、ある意味で「キャピタリズムが終わった」との話が出てきました。今日の市場では、投資先のバリエーションが少なく、(投資資金の)カネ余り状態になっているということはご承知の通りです。一方、企業価値を測る方法は、これまでの「ヒト・モノ・カネ」ではなく、「タレント(才能や技能)・データ・テクノロジー」の3要素に変わっていくのではないかと私は見ています。
これはあらゆる経済活動が本格的にデジタル中心になりつつあるためです。求められる人材像が変わり、同時にその人材が生きるためのデータやテクノロジーが非常に重要になっていくという動きです。佐渡さんから見て、企業のデータ活用度はどのように変化していると感じますか?
佐渡: まず、今やデジタルと経営は切り離せないものになっているので、経営に携わるならデジタルインパクトへの感度を高めていなければならない時代だと言えます。また、確かに、データ活用のあり方も変わっていますし、タレントの重要性も増しています。しかし、肝心の「どのようにデータ活用を行なうか?」というところは議論が追いついていないように感じます。
これまでの終身雇用制度が終わり、企業の元で働くという考え方から、個人が直接企業と契約する関係になっていくとします。するとタレントそれぞれが企業の求めるファンクションとどう合致するか、マイクロな目的に基づきデータを見てアロケーションするという、データドリブン経営にシフトしていくことになると考えます。ここで課題になるのは、企業のタレントに対する概念です。例えば「なるべく社内で」というようなトラディショナルな考えではスピードに追い付きません。大切なのはデジタル時代に求められる付加価値を発現するために、必要なデジタルタレントを社内外から柔軟に調達し、編成していける組織の柔軟性だと思っています。
デンリ: そもそもテクノロジーを中心に据えている企業はビジネスを推進するにあたって儲けを考えていない傾向があるように思います。様々な要素はあると思いますが、すでに「タレント・データ・テクノロジー」があれば資金には困らない、というモデルを理解しているのでしょう。
10年ほど前から「いいものにはお金を払う」というふうに所有者マインドは変化しています。だからこそ、カスタマーファーストで考えるのが当然になっていて、「タレント・データ・テクノロジー」が重視されるというわけです。
課題は、レガシー企業が今後どのようにこの変化に向き合うか、ということです。そうした場面で私たちのような企業がサポートしなければならないですね。
経営者は「上昇カーブに転じるまで我慢できるか?」問われる
茶谷: 今、老舗企業が新興企業に立場を揺るがされるような姿はたびたび見られます。この背景には、「リニアな発想か、エクスポネンシャルな発想か」という違いがあるのでしょう。
もちろん、デジタルの法則であるエクスポネンシャルな考えへのシフトが欠かせないのですが、グラフで描くとエクスポネンシャルの場合、カーブが非常に緩く進んである時点で急上昇する、という特徴を見せます。停滞期はリニアの方が力強い伸びを見せるため、それに慣れていると成長の経過に対して不安を感じることがあるかもしれません。経営者たちはその急上昇のタイミングまで我慢できるかを試されることになると思います。
佐渡: 確かに社内外でイノベーションを起こすにしても、新規ビジネスを立ち上げるにしても、エクスポネンシャルな考え方は重要です。それに加え、ビジネスモデルの違いによる意思決定のメカニズムの違いを理解することも欠かせません。
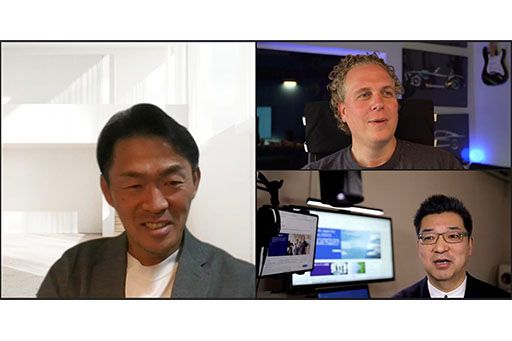
私は、これまでと同じオーナーが引き続きオーナーシップを取るべきかどうかは、慎重に判断すべきと思っています。なぜなら、意思決定の不確実性もスピードも、これまで染みついてきた事業とは別物だからです。その根本的な違いを無視して意思決定する体制を見誤ると結果、イノベーションは起こせない、と考えることが重要です。
茶谷: 確かに同じ思考の人が意思決定すると変化がない、というケースは多々ありますね。
とても興味深い例として、音楽レーベルのトップ層の振る舞いが挙げられます。彼らは必ずしも扱っている全ジャンルの音楽を理解しているわけはなく、新進気鋭のアーティストの発掘は“目利き”となる人を信じて任せるそうです。その目利きにも過去の実績などがあるので一概には言えませんが、ロジックで説明できない感性の部分や凄みに対する感度が経営者には求められているのでしょう。
デンリ: 私は「レガシーを作る会社か、守る会社か?」という議論を度々していますが、茶谷さんの話と非常にリンクしていると感じました。
会社を“経営”するか、“管理”するか?創業のDNAは会社を救う

茶谷: 今は高レベルな内部統制が求められるので、事業ごとの立て付けが強く作用しすぎる場合もあるのかもしれません。しかし、例えば日本の企業では「事業部長と同期だ」という“憎めないおじさん”が現場にいて、現場で出た良いアイディアをアポもなく同期の事業部長に紹介しに行く、ということが起こっていました。
ある意味でこのおじさんたちは「ビジネスの受粉役」になっていて、アイディアをビジネスに結実させてきたのだと思います。現場の人間は「まだ完成していないから」と、進行中のプロジェクトを隠したがる傾向がありますが、「これはおもしろいからあのプロジェクトと合わせてみては?」とか「この取り組みはあちらでやる方がより成果が上がりそう」と、横をつなげていくような役割を担う人がいたものです。企業文化としてそういう存在があるとやはり強いように感じます。
佐渡: 創業風土がそうした「受粉役」を生み出し、生かしているのだと感じました。まだ創業時のDNAが残り、受け継がれているということなのでしょう。
ゼロかイチかの変局の時代は、これまでのように管理統制でスケールを作ってきた時代とは明らかに異なります。ビジョナリーなものが求められる時代であるからこそ、自分たちが立ち戻れる拠り所がないとダメになることは多いのではないでしょうか。
茶谷: 会社は管理して運営するものではなく、経営するものですからね。
佐渡: 最近のトヨタ自動車からも創業の精神が感じられますね。豊田章男氏が創業家出身でトヨタのDNAを引き継いでいたという部分もあるかもしれませんが、それだけではないでしょう。
豊田氏は「モビリティカンパニーに生まれ変わります」と未来を語っておられますが、創業の精神というのはどこかにそうした「社会に貢献したい」というビジョナリーな部分があると思います。それは今風に言うとSDGsにリンクしやすいものだとも言えます。
デジタルの時代、つまり根本からビジネスモデル・業界ルールが変わる時代においては誰しもが不確実な未来に不安を抱えます。だからこそ、“管理する”ことよりも“未来を示す”ことこそが経営者の責務だと思います。
デンリ: 「ハイパーパーパス」ですね。私は若い頃、まだビル・ゲイツが現場にいたころのマイクロソフトで仕事をしたことがありますが、「コンピューターの力で自分の人生をより良くする」という考え方がすべての現場でしっかり染み込んでいたように思います。だから企業・社員の振る舞いにもその考え方が反映されていく、というわけです。
本来ならその精神が企業のKPIにならないといけないですし、GAFAはOKR(Objectives and Key Results:目標とキーとなる成果)をうまく利用して創業の精神を広く意識させていると感じます。
決まった答えがない時代にどう価値創造するか?
茶谷: 今回も様々な話題が上がりましたが、どれもVUCAの時代を感じさせるものです。そうした中で私たちが素早く柔軟にビジネスを推進するためには、「とりあえず食材を刻んでおいて、注文が入ったらチャーハンでも中華丼でも、なんでもすぐ作れる」という中華料理店のようなあり方はひとつの解だと思うようになりました。佐渡さんはいかがでしょうか?
佐渡: KPMGコンサルティングとしては、「この部分のデジタライゼーションをサポートしてほしい」というようなことではなく、先に紹介した3つの能力を埋め込んだトランスフォーメーションを、プランニングから実行まで企業のブレーンとして価値提供できるよう進んでいきたいと考えています。
そのためにはどのようなテクノロジーを編み合わせるか、その時どのような価値が描けるのか、想像していかなければならないでしょう。クライアントやマーケットが注文してくるよりも先にこちらから仕掛けていく、そういうスタンスもとても大事だと思っています。これはKPMGコンサルティングとKITが一緒になって取り組んでいけることだと考えています。
茶谷: それはワクワクしますね。これまでとは違うバリューやメソドロジーで、「できない」と思われてきたところを「できる」に変えていきたいですね。

KPMG Ignition TokyoのLinkedInをフォローして最新情報をチェックしてください。